今回は、職業が自衛隊の父から常日頃から叩き込まれてきた『生きるための知識』を記事にしていこうと思います。自分の身や大切な人を守る時に役に立つのは自分だけなので、「いざッ!」という時の知識として持っておいてください。
なぜ!こんな記事を書いたかと言うと、防災意識がここ数年の間に凄く高くなってきたからです。地震、豪雨、津波、台風などの自然災害も多いですが、遭難、計画停電、交通災害、火事、労働災害などの人為災害もニュースで目にすることが当たり前になってきています。いつどのタイミングで被災者になるか分からないご時世なので、実践が出来なくとも『pukupukuのブログに役立ちそうなこと書いてたな!』と思っていただけるだけで十分です。被災した時やキャンプで使える情報を記事として蓄えて行くので、困ったときの参考にして下さい。
とりあえず大好きなキャンプ飯がメインになると思いますが、ご家庭でも出来るのでぜひ試してくださいね。٩( ''ω'' )و
1.メスティンの魅力
1-1.メスティンとは
スウェーデン発症の企業『トランギア』が発売したアルミ製の調理器具になります。山好きやハイカーの中では人気が高く、シンプルなデザインながらもコンパクトで用途の幅が広いことがポイントのようです。飯ごうとしてご飯を炊くのはもちろん、煮る・蒸す・炒める・燻すのように多機能であらゆる調理法に対応しているため、お値段以上に感じる調理器具になっています。
1-2.メスティンについて
①.サイズ
サイズが2種類あります。ノーマルサイズは1人用でご飯1合~2合程度炊くことができます。ラージサイズは2~3人用でご飯3.5合炊くことができます。

②.使用前の下処理
メスティンを購入したら、調理前に行うことがあります。それは「バリ取り」と「シーズニング」です。
- バリ取りについて
軍手をしてサンドペーパーで本体や蓋のフチの廻りを磨きましょう。磨き終わりのサインは、指で触てみてざらつきが感じなくなれば完了です。
- シーズニングについて
米のとぎ汁をメスティンが浸かる量まで鍋に入れて火にかけます。15~20分ほど煮込めば完了です。
米の被膜がメスティンとなじみアルミ臭の軽減や火にかけた時の黒ずみ防止になります。
③.メスティン収納術
メスティンは持ち運びにも優れていて、料理以外には収納ボックスとして持っていくことができます。私はすぐにお湯が沸かせるように固形燃料やポケットストーブを常に入れています。いちいち探さないで良いので便利ですよ。('ω')ノ


2.実際にご飯を炊こう!
メスティンの下処理をしたら、いよいよ使ってみましょう。
今回はノーマルサイズのメスティンを使用するやり方を紹介します。ラージサイズでも基本的に同じなので、参考にして下さい。
2-1.材料
・お米 : 1合(180ml)
・水 : 200ml
※計量カップがなくとも、メスティンには本体とハンドルをつなぐ2つの結合部(リベット)があり、この丸の直径に合わせて水の量を入れれば大丈夫です。

・メスティン(ノーマルサイズ)
・タオルや手ぬぐい等の布(仕上げる時に必要)
2-2.手順(ガス・電気などのやり方)
1⃣.しっかりと吸水させる
30~1時間程度お米に水を吸水させて下さい。

2⃣.約17~20分炊く
途中で噴きこぼれるので、必要に応じて上に重石を置いてください。(缶詰を置くと温められるのでおススメです。)15~20分ほどでパチパチという音がしなくなったら火から下ろします。(置いたままにすると焦げるので、火のあたる場所を変えながら炊きます。)

3⃣.逆さまにして蒸らす
熱いので、軍手や革手袋をして布などにくるんで逆さまにします。15分ほどそのまま放置して蒸らしてください。(ひっくり返すことで底にある水分が全体に行き渡ります。)

4⃣.完成
メスティン自体がまだ熱いので、軍手や革手袋をして持つようにしてください。
ホクホクでいつもと違ったお米の味わいに食も進むと思いますよ。( *´艸`)
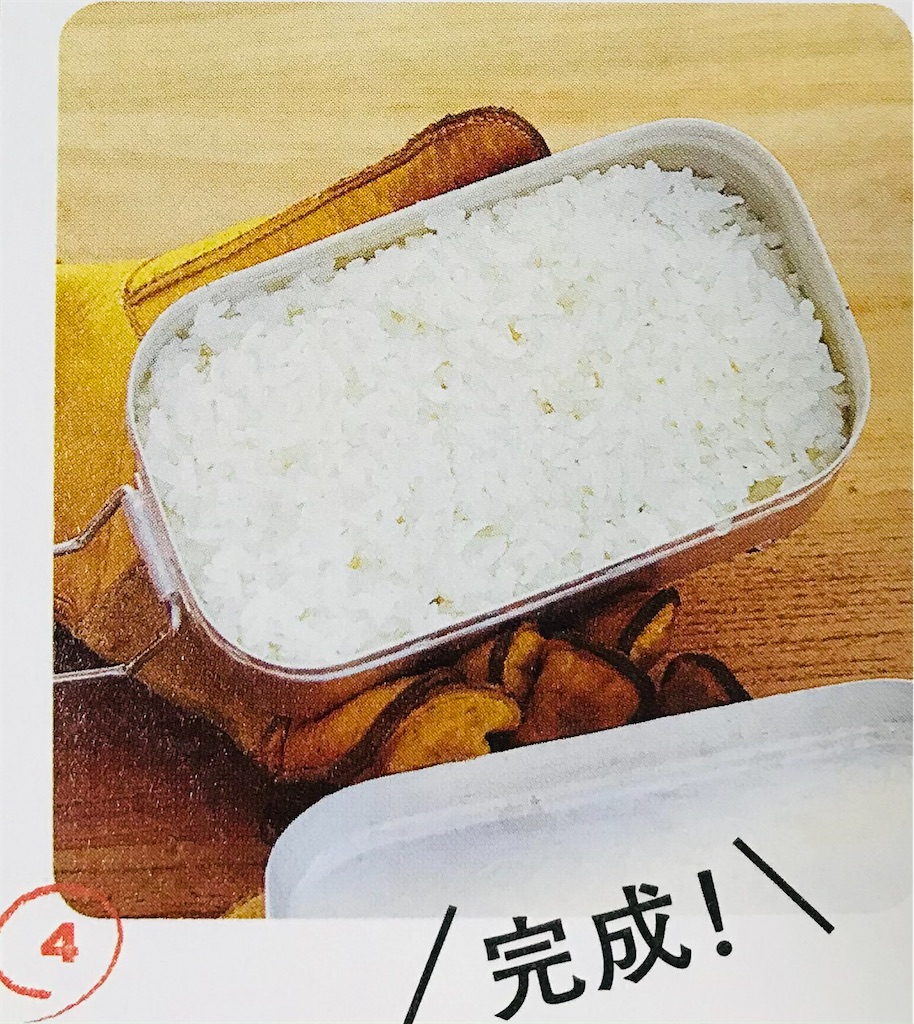
2-3.手順(固形燃料の場合)
固形燃料の場合は、基本放置です。٩( ''ω'' )و笑
今回は居酒屋などで目にする固形燃料を使って紹介します。

1⃣.吸水を済ませたお米をそれぞれ火にかけます。
放置するため、蓋の上に缶詰を載せて下さい。

2⃣.10分ほど経過すると、噴きこぼれが始まります。

3⃣.だいたい28分ほどで固形燃料も尽きるので、この後は軍手をしてメスティンをひっくり返し布で巻きます。

4⃣.15分ほど蒸らした後、美味しそうに炊きあがります。
真ん中の部分が多少お焦げができますが、これが美味しかったりします。
初めての方でも簡単に出来るので、是非やってみて下さい。

3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回参考にしている内容や写真は、こちらの本から抜粋しています。気になった方はこちらからどうぞ。
最新の技術を学ぶことも仕事上で必要かも知れませんが、過去の『モノが無い生活』を知ることも日常生活を送る中では必要なのかもしれませんね。
情報がたくさん飛び交う世の中だから、自分で考えて、行動して行く必要があるように思います。
生活に役立つ記事をこれまでも、そしてこれからも書いていきますのでよろしくお願いします。それでは(@^^)/~~~。